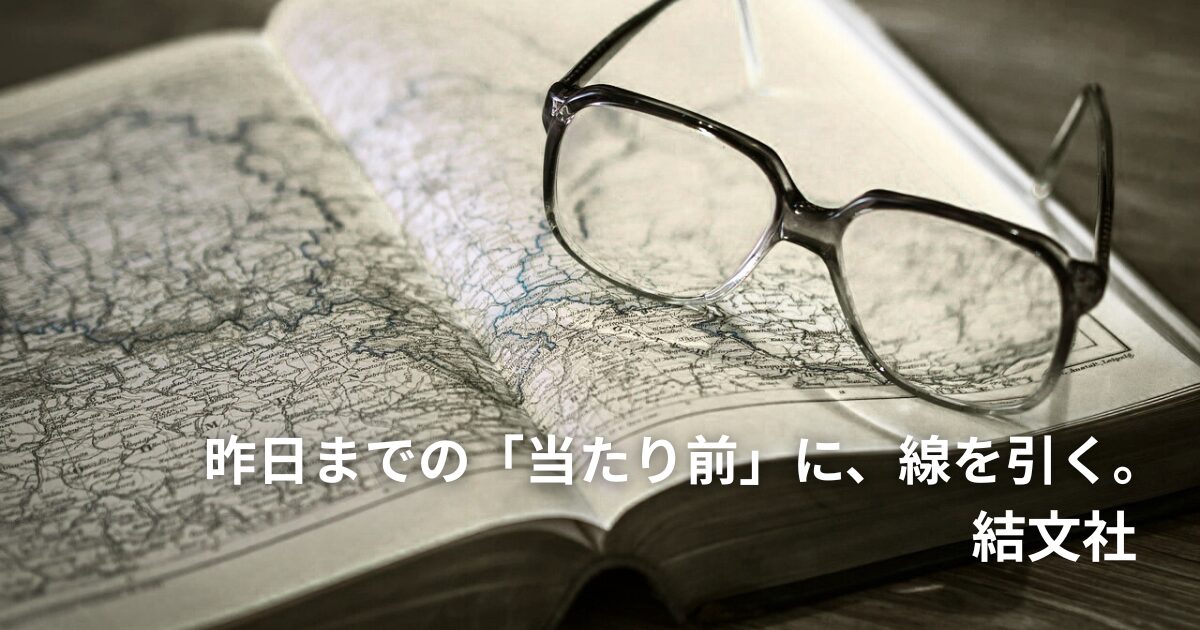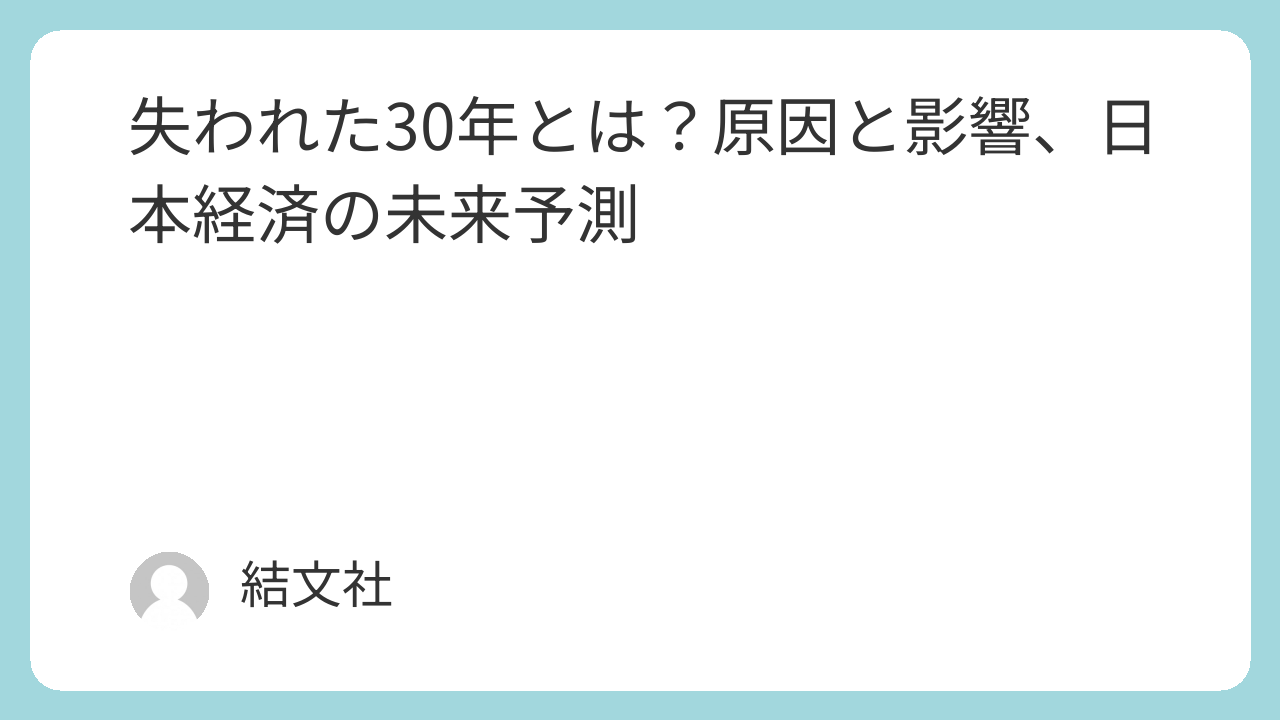「失われた30年」とは何か、なぜ日本経済は長期にわたって停滞したのか。この言葉は、多くのメディアで語られていますが、その本質を正確に理解している人は少ないかもしれません。
本記事では、1990年代初頭のバブル経済崩壊から現在に至るまでの経済状況を、国際比較や具体的なデータを用いて、わかりやすく解説します。失われた30年の原因を理解することが、今後の日本経済の展望、そして私たちが取るべき対策を見出すカギとなるでしょう。
失われた30年とは?1991年から続く経済停滞の期間
「失われた30年」とは、一般的に1991年のバブル崩壊を起点として、現代まで続く約30年間の日本経済の長期停滞期間を指す言葉です。
この言葉は当初「失われた10年」「失われた20年」と呼ばれていました。しかし停滞が長期化するにつれて、呼び方が変わった経緯があります。停滞期からの脱出の兆しが見えた今、「失われた30年」が、最終的な呼称です。
「失われた30年」の定義と期間
「失われた30年」に、明確な定義はありません。ただ、1991年から2020年代初頭までの期間を指すのが、一般的です。
この間の日本経済は、低成長、デフレーション(物価の継続的な下落)、そして金融システムの不安定化に苦しみました。
「失われた30年」の実質GDP成長率
この期間中、日本の実質GDP成長率は他の先進国と比較して著しく低迷しました。
実質GDPとは、「実際に生産されたモノやサービスの『量』がどれだけ増減したか」を示す指標です。国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額(GDP)から、物価の変動による影響を取り除いて算定します。
そしてGDP(国内総生産)は、国内で生み出された付加価値(儲け)の合計です。この生み出された付加価値、つまり国全体で稼いだパイ(GDP)は、企業と家計で分け合います。「生産(GDP)= 分配(所得)」という関係です。
ということは、実質GDPが停滞するとはすなわち、国全体で生み出す付加価値のパイが、物価の変動を除いても大きくなっていないことと同義です。
パイの大きさが変わらない以上、それを分け合った結果である所得の総額も増えません。企業の利益が増えなければ、従業員の給与を上げる原資が生まれません。これが、実質GDPの低迷が所得水準の停滞に直結する根本的な理由です。
多くの国が経済成長を続ける中で、実質GDPは低迷した日本の国民の所得水準はほとんど向上しなかった30年。その結果、国際社会における日本の経済的な地位は、相対的に低下しました。
データで見る「失われた30年」
言葉だけでなく、実際のデータを見ると「失われた30年」の影響はより明確になります。
株価指数に見る日米の格差
株価は、投資家による企業の将来性や経済全体への期待感を反映するため、「経済の体温計」に例えられることがあります。その国の経済が成長すると期待されれば株価は上がり、逆であれば下がります。
この30年間で、日米の株価には決定的な差が生まれました。例えば、アメリカの代表的な株価指数である「S&P 500」は、日本のバブル経済が頂点にあった1989年末から30年後の2019年末までの間に、約9倍にまで上昇しています。
一方、日本の日経平均株価は、1989年末につけた史上最高値(38,915円)を、その後30年以上も更新できませんでした。この事実は、日本の企業価値や成長期待が、世界から大きく遅れを取っていたことを象徴しています。
IMD世界競争力ランキングでみる失なわれた30年
企業の生産性や政府の効率性などを総合的に評価するIMD(国際経営開発研究所)の世界競争力ランキングにおいて、日本はかつて1位(1989年~1992年)を誇っていました。しかしその順位は下落を続け、2022年には過去最低の34位まで転落。日本の国際的な競争力の低下が、浮き彫りになっています。
失われた30年を招いた3つの構造的原因
なぜ日本だけが、これほど長期の停滞に陥ったのでしょうか。その原因は、複数の要因が複雑に絡み合っていますが、主に以下の3つが指摘されています。
原因1:不良債権処理の遅れ
バブル崩壊により、企業の持つ土地や株式などの資産価格が暴落。多くの企業が融資の返済困難に陥り、銀行の貸出金は次々と不良債権となりました。
しかし、多くの金融機関は抜本的な処理を先送りしました。その背景には、「土地の価格は必ず上がり続ける」という戦後日本の「土地神話」や、体力のない銀行が潰れないよう金融業界全体を国が守る「護送船団方式」という当時の慣行がありました。これらの要因から「いずれ地価は持ち直すはずだ」という希望的観測が生じ、問題の先送りが続きました。
結果として、大量の不良債権を抱えた金融機関は経営体力を失い、企業の成長に必要な資金を供給できない「貸し渋り」が発生。経済全体の血流を滞らせる大きな原因となりました。
原因2:ロストジェネレーション世代の創出
経済の低迷は、労働市場にも深刻な影響を及ぼしました。バブル崩壊後、企業は新卒採用を大幅に抑制。1990年代半ばから2000年代前半の「就職氷河期」に社会に出た世代は「ロストジェネレーション(ロスジェネ)」と呼ばれています。
この世代の多くが、不安定な非正規雇用の立場でキャリアをスタートせざるを得ませんでした。その結果、十分な収入やスキルアップの機会を得られず、消費の低迷や少子化の一因になったとも指摘されています。つまり、ロスジェネ世代の不遇は、日本企業が人材育成という未来への投資を怠った結果であり、国全体の生産性が伸び悩む大きな原因となったのです。
原因3:デフレマインドの定着
「デフレ」とは、モノやサービスの価格(物価)が全体的に下落し続ける現象です。「失われた30年」の中でも、特に1990年代後半から約20年間にわたりこのデフレ状態が続きました。
その結果、人々の心に「給料は上がらないのが当たり前」という考えと共に、「明日は今日よりモノが安くなる」というデフレマインド(社会通念・ノルム)が深く根付いてしまいました。
一見すると、消費者にとってモノの値段が下がるのは良いことのように思えます。しかし、多くの人が「どうせ安くなるなら、買うのは後でいい」と考える「買い控え」を始めると、経済全体で悪循環が始まります。
- 消費の先送り → モノが売れなくなる
- 企業の売上減少 → 企業の利益が減る
- 賃金カット・雇用悪化 → 人々の所得が減り、将来が不安になる
- さらなる消費の低迷 → 1に戻る
この経済が縮小していく悪循環(デフレスパイラル)が、日本経済を長期間にわたって蝕む大きな原因となったのです。
「失われた30年」は終わったのか?現状と今後の展望
2024年3月、日経平均株価が史上最高値となる4万円を突破し、「失われた30年からの脱却」という言葉がメディアを賑わせました。これは本当に「終わり」の始まりなのでしょうか。
日経平均株価4万円突破は「脱却」の兆候か
株価の上昇は、海外投資家からの日本企業への再評価や、企業の収益力改善が背景にあり、経済の潮目が変わりつつあるポジティブな兆候と捉えられます。
景気回復の実感が伴わない理由
しかし、多くの国民が「景気が回復している」という実感をなかなか得られないのも事実です。その最大の理由は、物価の上昇に賃金の上昇が追いついていないためです。生活必需品の値上がりが家計を圧迫し、可処分所得が伸び悩んでいる状況では、好景気を実感するのは難しいでしょう。
構造的課題:デフレからの完全脱却と持続的な賃金上昇
「失われた30年」から完全に脱却するには、一時的な株高だけでなく、デフレからの完全脱却と、それを支える持続的な賃金と物価の上昇(インフレ)が不可欠です。企業の生産性を高め、その果実が適切に賃金として分配される好循環を生み出せるかが、今後の日本経済の鍵を握っています。
停滞の時代を乗り越えるための視点
マクロ経済の変化を待つだけでなく、個人や企業レベルでも「失われた30年」がもたらした構造から脱却する視点が求められます。
個人の対策:デフレマインドからの脱却と資産形成
長年続いたデフレ環境は、「現金が最も安全な資産」という考えを浸透させました。しかし、インフレが進行する局面では、現金の価値は目減りしていきます。
デフレマインドから脱却し、NISAなどを活用した資産形成を通じて、インフレに負けないポートフォリオを構築することが、個人の資産を守り、育てる上で極めて重要になります。というのが、経済学や金融の専門家の言葉としてよく語られます。
資金にゆとりがあり資産運用を考える際は、リスクを考慮した上で、個人で許容できるリスクの歯に内において、慎重にご検討ください。
ただし資産形成は、必ずリスクを伴うため、筆者は懐疑的です。特に資産が少ない場合、大きなメリットは期待しにくい実情を、考慮する必要があるでしょう。あくまでも資産運用は、余剰資産のある人を対象にした商品です。
では、資産が少ない者は、どうやって目減りする財産を守ればよいのか?という疑問も生じるでしょう。これについては、資産運用の余力がない場合は、現金価値の目減りは避けられないというのが、現在の経済学的見解です。
その代わり、収入を増やすために副業したり、支出を減らすことで家計を守るなどの対策が考えられます。ご自身の事情に合わせた対策が必要です。
企業の対策:生産性向上とイノベーションへの投資
企業は、安売り競争から脱却し、付加価値の高い製品・サービスを生み出すために、イノベーションへ投資することが不可欠です。DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や、従業員のスキルアップ支援などを通じて生産性を向上させ、賃上げの原資を確保することが、企業の持続的な成長に繋がります。
まとめ
「失われた30年」とは、単なる不景気ではなく、バブル崩壊後の不良債権処理の遅れ、労働市場の硬直化(ロスジェネ問題)、そして人々の心に根付いたデフレマインドという複数の構造的な原因が絡み合って生まれた、日本の長期経済停滞です。
近年の株価上昇は明るい兆しであるものの、多くの人がその恩恵を実感するには至っていません。この停滞から完全に抜け出すためには、企業による生産性向上と持続的な賃上げ、そして私たち一人ひとりがデフレマインドを克服し、新しい経済環境に適応していく姿勢が求められています。
参考資料一覧
課題認識はすでに十分 日本の競争力復活に向けて試されるリーダーの実行力
停滞感が強まる日本経済 ─ 本質的課題は「デフレ脱却」から供給制約へ変化 ─ | みずほリサーチ&テクノロジーズ
第1節 日本経済の動向と持続的な回復に向けた課題 – 内閣府