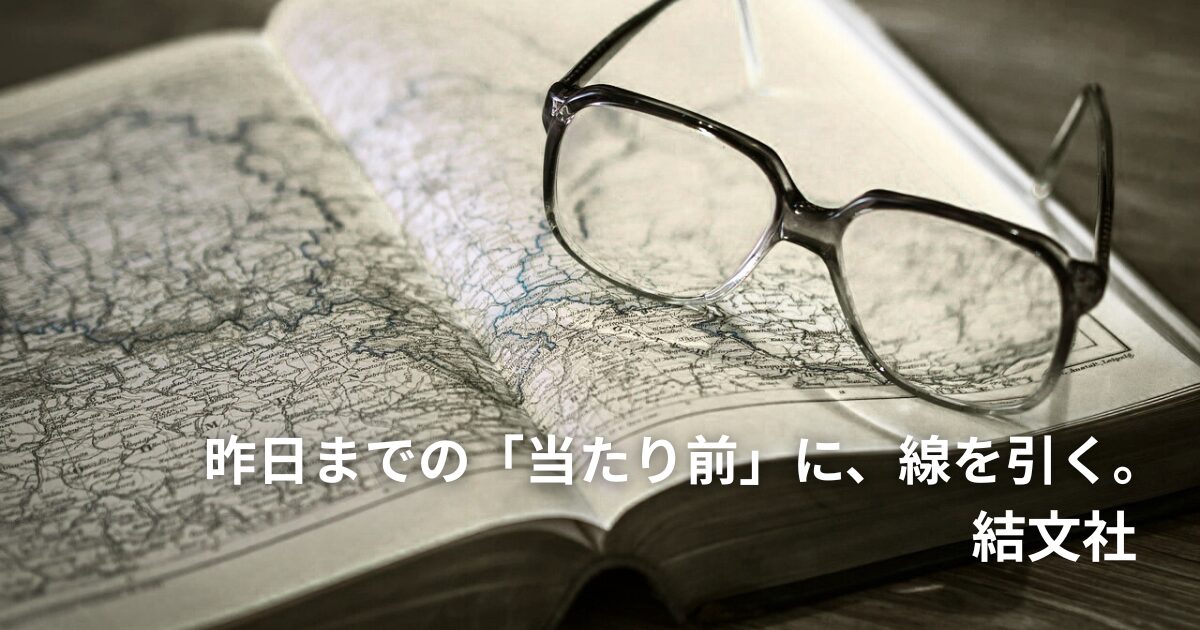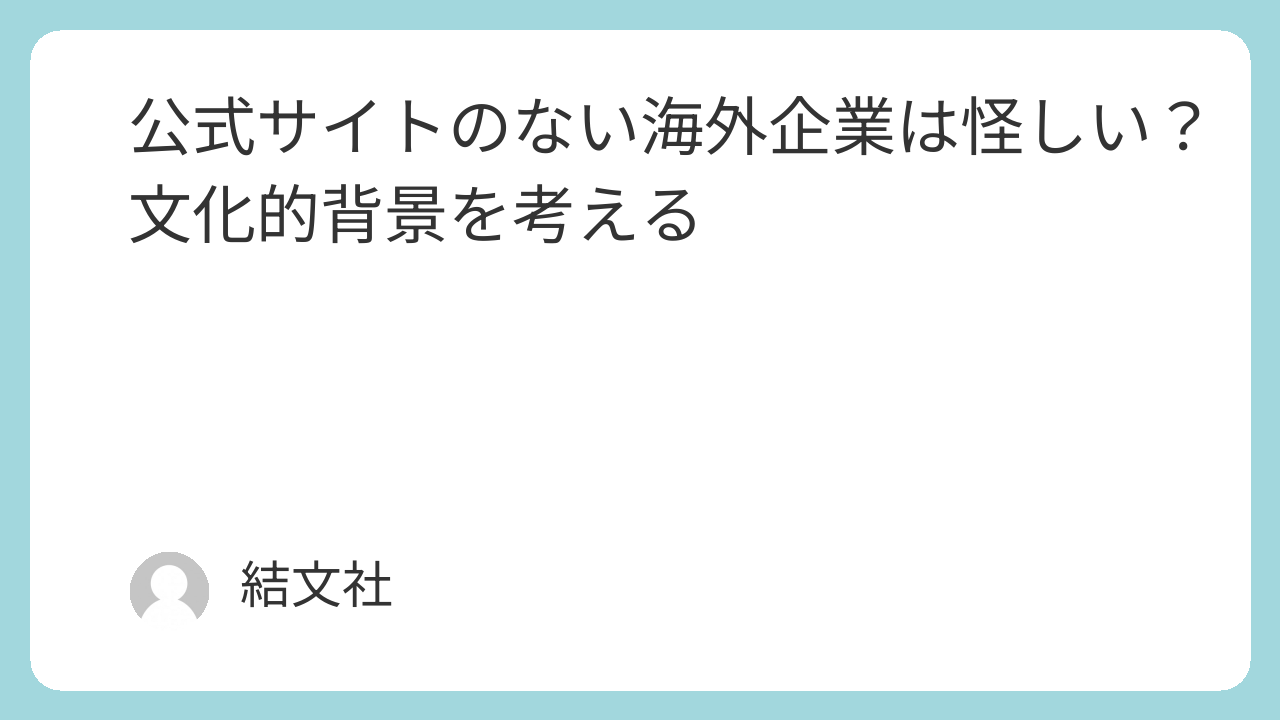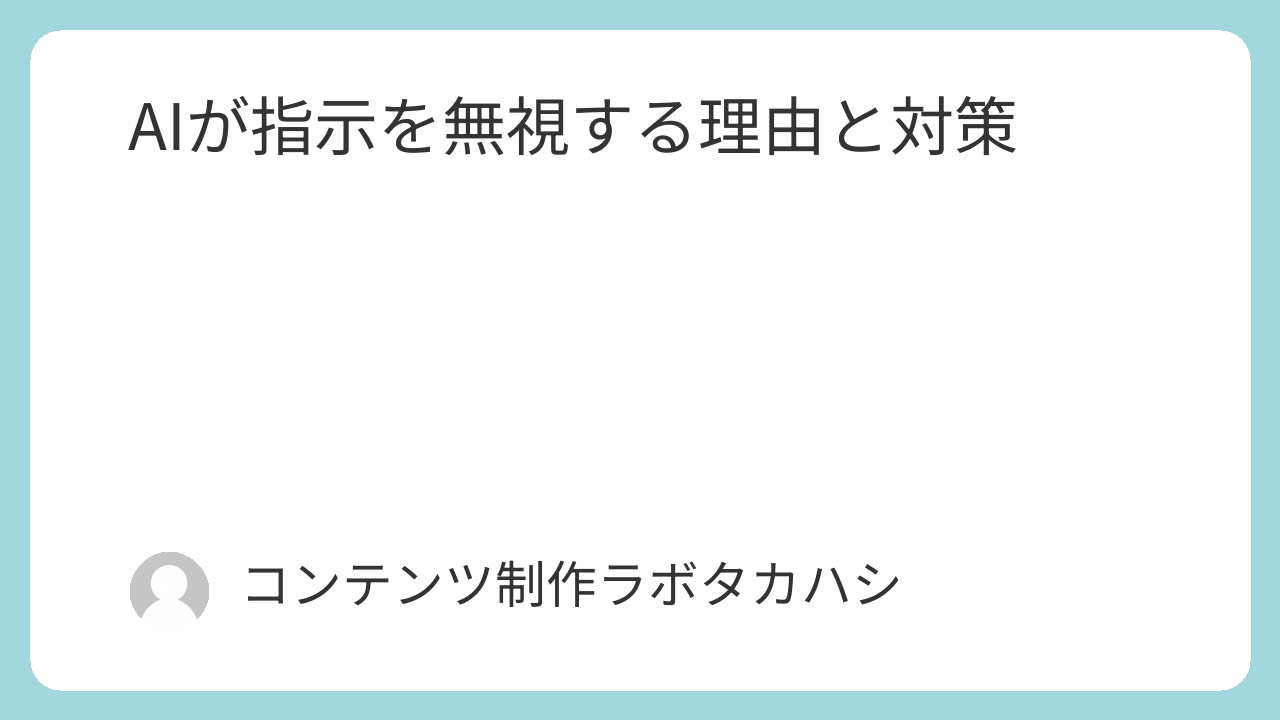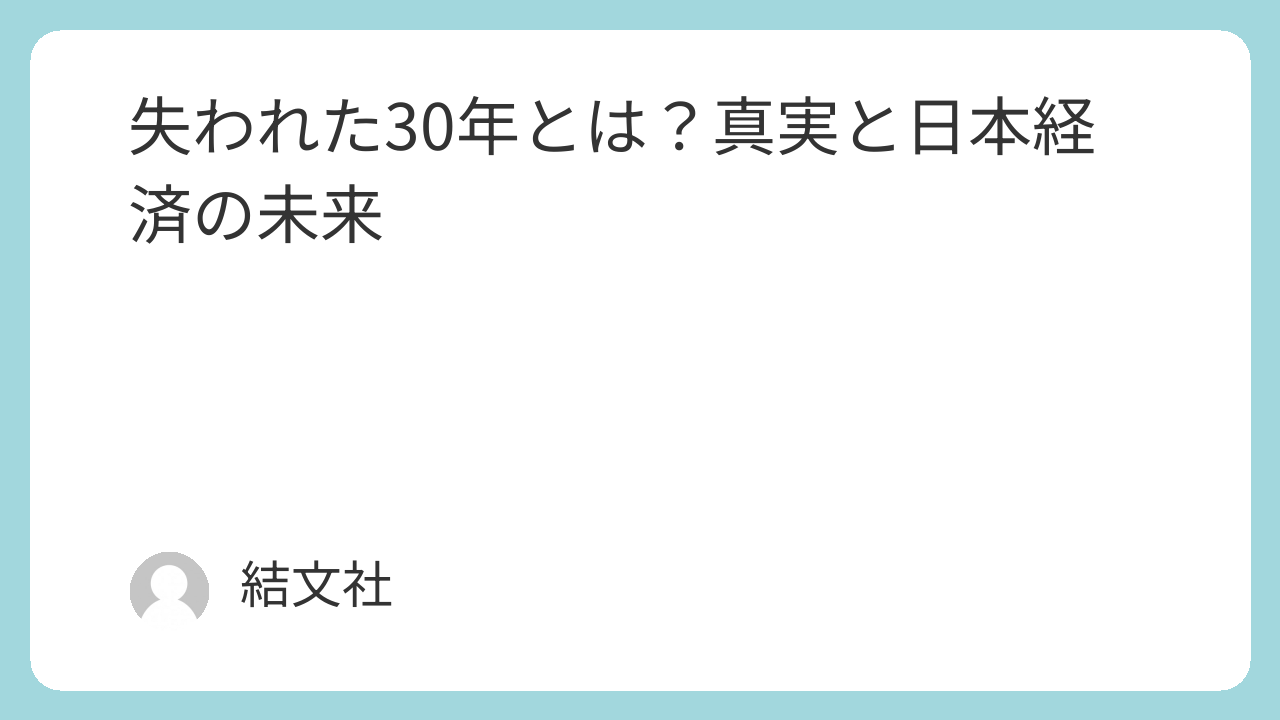オンラインショッピングで魅力的な商品を見つけたとき、企業名で検索しても公式サイトが見つからない。しかし、その企業のストアはAmazonにはしっかり存在している!?
「やっぱり、海外企業は怪しいな」
「これでは、トラブルが起きたときに、連絡先がわからなくなるのでは?」
「どうせ、品質も信用できないに決まっている」
海外企業だからという理由で、そう短絡的に判断していませんか?特に中国企業によくある傾向なため、ネガティブな先入観の影響を受けることもあるでしょう。
しかし、その「怪しい」という感覚は、本当に正しいのでしょうか?もしかしたら、それは日本の常識にとらわれた、時代遅れの考え方かもしれません。
公式サイトを持たないという選択は、国によっては、最も合理的で賢い戦略です。「怪しい行為」ではなく、その国の社会体制や文化の中で生まれたもの、という可能性が多々あります。
この記事では、この文化的な違いを深掘りし、私たちの先入観を問い直すきっかけを提供します。
なぜ公式サイトを持たない企業が存在するのか?
ウェブサイトを持たない理由には、国や地域によって異なる背景があります。ここでは、中国の事例を参考に、その合理性について考えてみましょう。
1. 煩雑な手続きとコストという「見えない壁」
日本では、企業だけでなく個人でも、自由にWebサイトを運営できます。Webサイトの運営に際して、国の許可を取得する義務はありません。しかし国によって、ウェブサイトを運営するために、行政の許可を得なければならず、さらに申請に際して多大な費用がかかるケースがあります。
その筆頭である、中国の例を見てみましょう。
中国では、Webサイトを運営するに際して、ICP(Internet Content Provider)登録が義務付けられています。ICPとは、中国のサーバーを利用してウェブサイトを公開する際に、政府への登録を義務付けるものです。
そしてこのICP登録の手続きは非常に複雑であると同時に、多くの時間と労力を要します。
<要件・手続き(一部抜粋)>
- 中国国内に登記された法人・個人
- 多数の書類提出が必要
- 申請から完了まで1ヶ月以上要するケースが多い
- Webサイトの責任者は、指定された場所での顔写真の撮影が必須
- ICP登録の専門業者に依頼することが一般的で、さらにコストがかかる
万が一にも政府からWebサイトの内容について指摘を受けることがあれば、顔写真を登録した責任者は、厳しく責任を追及されかねません。罰則を受けることも考えられます。
このように、中国企業にとってWebサイトを運営するハードルは、あまりにも高いのが実情です。そのため多くの企業は、自社ホームページに依存しないことを選択しています。
Webサイトを持つだけで政府の検閲を受ける可能性がある。これは、日本に暮らしている我々にとって、想像もしえない事実でしょう。Webサイトが存在しないという状況だけ捉えれば、「怪しいのではないか?」と思うのも、無理ありません。
しかし、特に他の企業やサービスの場合、その国の市場および政治的な事情があること。またその結果、あえて企業の公式Webサイトを開設していない可能性があるということを、理解する必要があるでしょう。
2. インターネット=「アプリ」という文化
国によっては日本とは全く異なるインターネット文化が根付いている場合があります。
先に例を挙げた中国では、2022年時点で中国のネットユーザーのうち スマートフォンでネットに接続している割合は99.6% と報告されています。これはつまり、中国でインターネットを使う人のほぼ全員がスマートフォンを使っている状況がある、といえるでしょう。
同様の傾向は、直近の統計でも維持されています。また日本貿易振興機構(JETRO)の報告によれば、2025年においても携帯電話(主にスマートフォン)による接続率は98.8%に達していることがわかっています。
| 中国 | 日本 | |
| スマホでのネット接続率 | 98.8~99.6% | 個人ベース80.5%世帯ベース90.5% |
| SNS主体の情報収集 | WeChat, WeiboなどSNSでの収集が主流 | SNS利用81.9%Webサイト・検索も約80%前後で併用 |
そして中国では、情報収集はWeChatやWeiboといったSNSアプリ上で行われるのが主流です。SNSプラットフォーム(抖音、快手、小紅書、哔哩哔哩、微博など)が、全ネット人口の85.7%(約10.71億人)をカバーしているというデータがあります。
ネット利用者向け主力SNSは、 WeChat(微信) および Weibo です。
- WeChatの月間アクティブユーザーは13億5,900万人(2024年1月時点)
- Weiboの月間アクティブユーザーは6億8,800万人(2024年)
これらのSNSは、ニュースや消費トレンド・商品情報の取得でも利用されています。特に若年層では、情報収集の中心的なツールです。
日本でもSNSの利用者は増加傾向ですが、Webサイトも併用しています。しかし中国の場合は、SNSアプリでの情報収集が主流です。
中国文化の中では、インターネット=アプリといっても過言ではありません。多くのユーザーの目に触れる可能性が低いにもかかわらず、運用には多大なコストがかかるWebサイトの運営は、ビジネスとして非効率的。
つまりWebサイトを持たない中国企業が存在するのは、ビジネスの観点でまったく不思議なことではなく、むしろ合理的な選択であるといえます。
3. 巨大プラットフォームを活用する「賢い選択」
こういった背景を持つ中国企業の場合、公式サイトを持たず、Amazonをはじめとする巨大プラットフォームでのみ販売する戦略をとっているケースを多く見受けます。これは、自国の文化的背景に対して最適化された、合理的な結果です。
- 煩雑な行政手続きを回避できる
- プラットフォームが提供する集客力と信頼性を最大限に利用できる
- 開発や維持にかかるコストを大幅に削減できる
日本の文化的な背景の眼鏡で見れば、公式サイトを持たないのは、品質の低い商品を売りつけて責任を問われた場合は逃げるための準備ではないか、と思われるかもしれません。
しかし、日本とは違う文化に根ざす企業であることを考慮した場合は、どうでしょうか。責任から逃げるための準備ではなく、巨大プラットフォームの信頼性と利便性を最大限に利用しているだけの、きわめて合理的で洗練された戦略である可能性が考えられます。
日本の常識を一度手放してみる
私たち日本人の多くは、自身が生まれ育った文化の中で、「公式サイトがあること=信頼できる企業」という方程式を、無意識のうちに作っています。しかしこの方程式は、グローバルな視点で見ると通用しないケースが多々あることがお分かりいただけたでしょう。
他国の企業は、彼らの社会体制の中で最も効率的であり、かつユーザーにリーチしやすい方法を選んでいるだけです。
公式サイトがないという理由だけで、「怪しい」「低品質」と決めつけるのは、もはや時代遅れの考え方でしょう。
- 品質の判断は、公式サイトの有無ではなく、商品のレビューや評価で判断
- 企業の信頼性は、SNSでの発信や顧客とのコミュニケーションで測る
最近は口コミを購入する企業も増えているため、レビューが一概に信用に足るとはいえない側面があります。ただ、自分自身の文化的背景に基づいた常識の観念で世界を計ることで視野が狭くなり、せっかくのチャンスを逃す可能性があることも、念頭に置くべきでしょう。
リスクを避けたい思いから、公式サイトをチェックするのは、妥当な判断です。しかし時には、「なぜ公式サイトがないのだろう?」と考え、さらに踏み込んで検証してみてはいかがでしょうか。文化的な背景の違いだけでなく、宣伝費用を最小に抑えて品質の向上に注力している企業努力の存在に、気づく可能性もあります。応援したくなる企業やサービスとの出会いに、つながることもあるでしょう。
これこそが、真の損失回避と利益の最大化につながる考え方ではないでしょうか。
まとめ:文化の多様性を受け入れるということ
公式サイトを持たない企業の商品を購入するかどうかは、もちろん個人の判断です。しかし、その判断の根拠を「怪しい」という漠然とした先入観に置くのではなく、「なぜ公式サイトを持たないのか?」という背景を知ることで、より本質的な見方ができるようになります。
特に日本以外の国の企業の商品やサービスの販売戦略を理解することは、現代社会の多様なビジネスのあり方を学ぶ、貴重な機会です。今回取り上げたような、公式サイトの有無だけで企業を判断するのではなく、多角的な視点から物事を捉えること。これこそが、情報過多な現代を賢く生き抜くための鍵ではないでしょうか。
参考出典
総務省、令和6年通信利用動向調査の結果を公表 | カレントアウェアネス・ポータル
2024年 中国で人気のSNS 8選~中国ネット規制や最新SNSトレンドを解説~ – 海外デジタルマーケティングブログ | i CROSS BORDER JAPAN