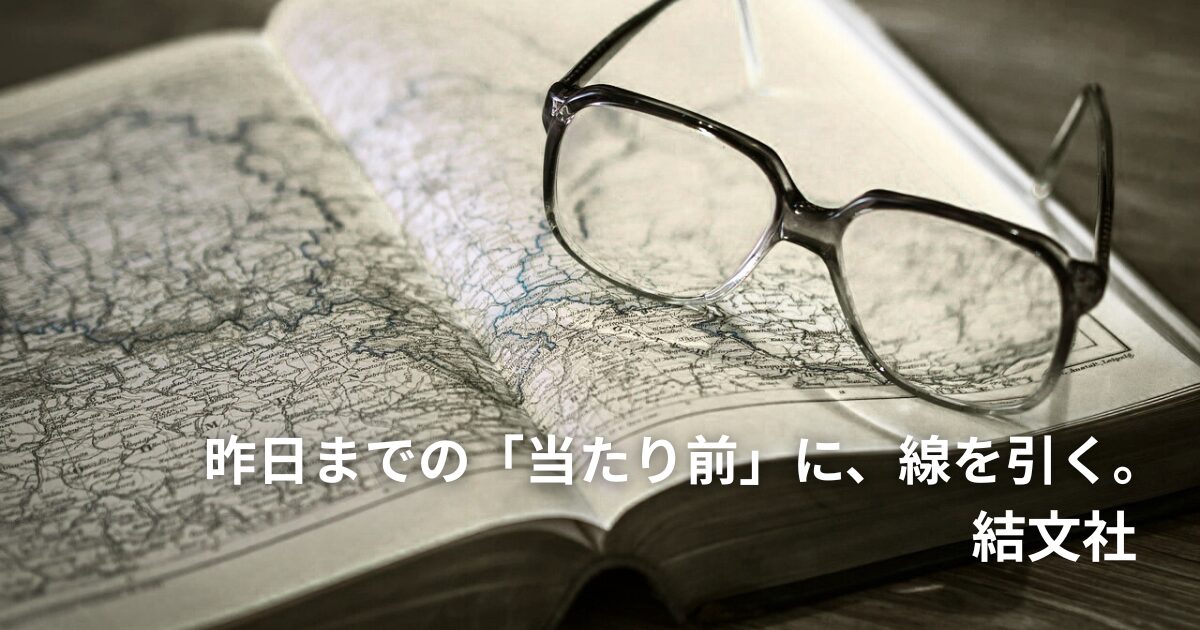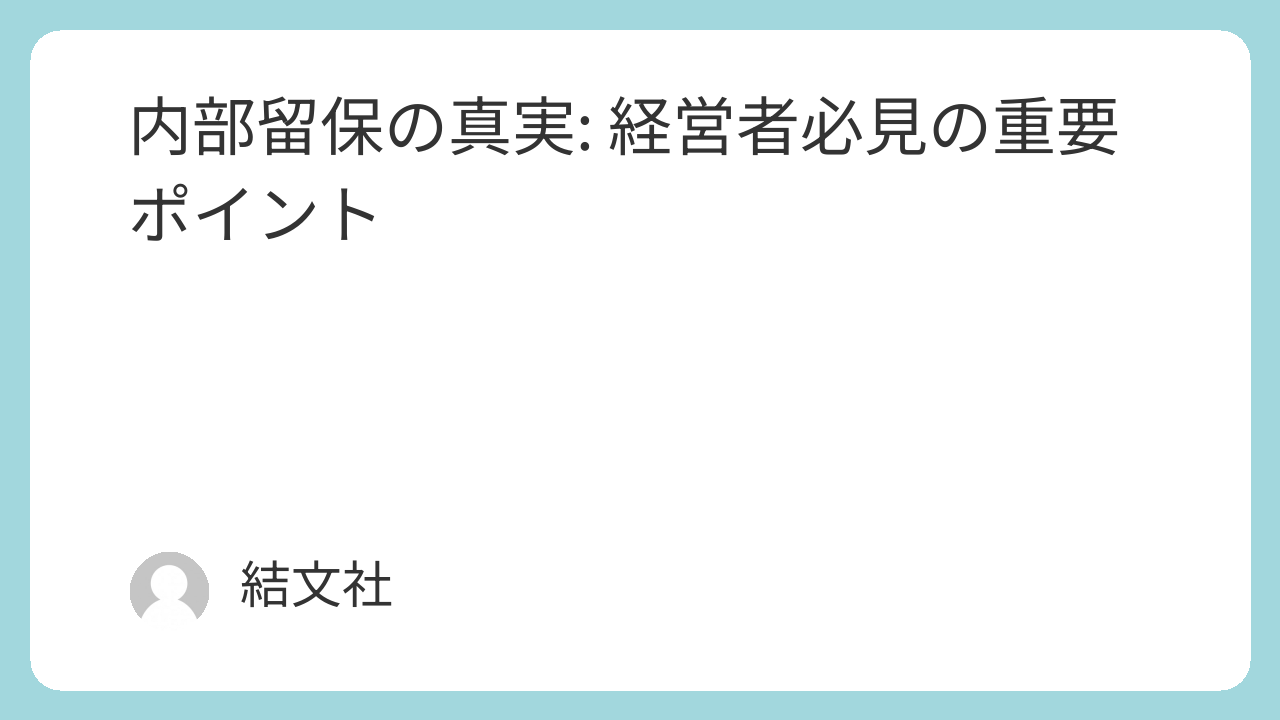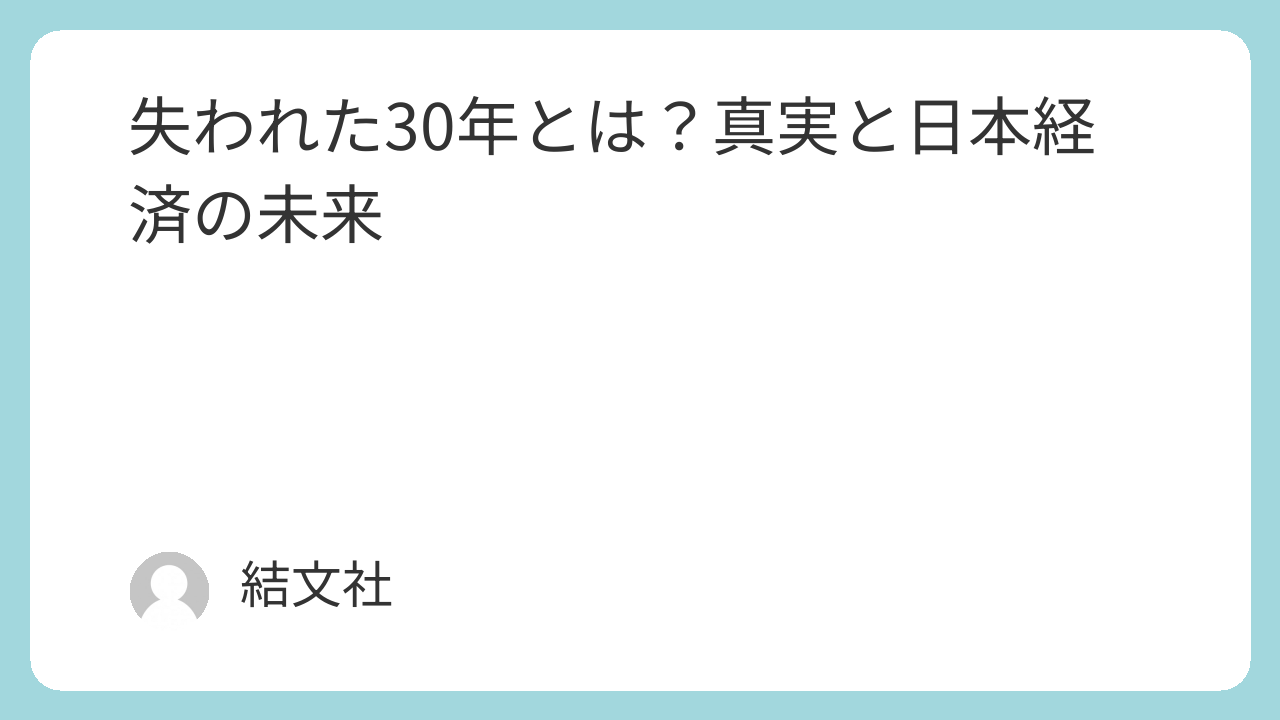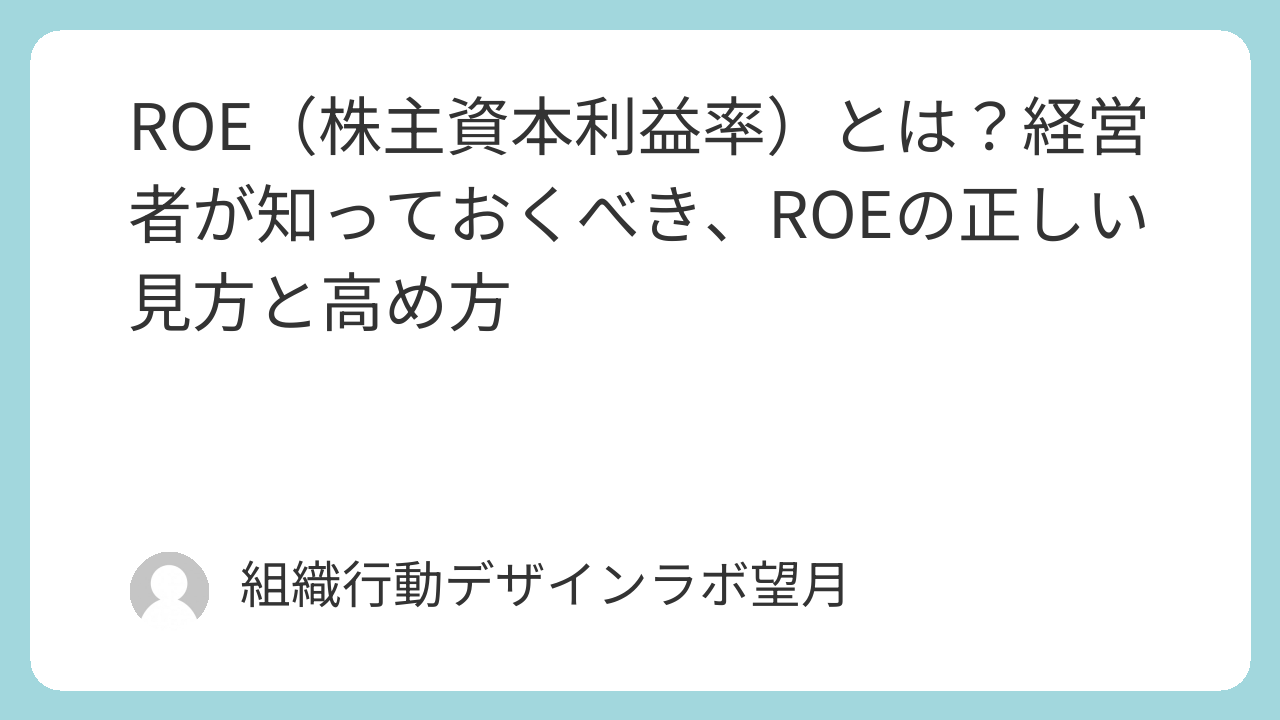「内部留保」という言葉が日々のニュースで取り上げられるたび、「企業が利益を還元していない」「給料を上げずに現金を貯め込んでいる」といった風に語られています。経営者としては、釈然としない思いを抱くのではないでしょうか。
メディアの論調や「内部留保」という言葉自体の印象も手伝って、多くの人が、内部留保とは「タンス預金のように企業内に眠っている現金」と誤解しています。しかし、それは大きな間違いです。
本記事では、内部留保の正しい意味から、日本企業における実態、そしてなぜ利益が出ても安易に給料に回せないのかを、企業経営者の視点から徹底解説します。この記事を読めば、従業員や株主に対して、不要に肩身の狭い思いをすることがなくなるはずです。
内部留保は「貯金」ではない。その正体とは?
まず、結論からお伝えします。内部留保は「現金そのもの」ではありません。
内部留保とは、企業が事業活動で生み出した利益のうち、税金や株主への配当を支払った後に社内に残ったお金の総称です。会計上は、貸借対照表の純資産の部にある「利益剰余金」として記載されます。
この利益剰余金は必ずしも、現金や預金として保有されているわけではありません。以下のような形で、企業の資産として存在しているのが、一般的です。
- 設備投資: 新しい工場や機械、オフィスの購入費用
- 事業投資: 他社へのM&A(合併・買収)や新規事業の立ち上げ費用
- 研究開発: 将来に向けた新技術やサービスの開発費用
- 在庫: 製造業における原材料や製品
- 売掛金: 顧客からの未回収の売上金
つまり内部留保とは、企業の成長や安定した経営のために、すでに活用されている「経営資源」です。
「内部留保があるのに給料が上がらない」は本当か?
「日本の企業は内部留保を溜め込んでいるのに、なぜ給料が上がらないんだ?」
これは、よく聞かれる意見です。しかし、「内部留保がある=給料を上げられる」という、単純な図式は成り立ちません。その理由について、内部留保の性質から理解をしましょう。
- 内部留保は「過去の利益」の積み重ね内部留保は、創業から現在までの利益の蓄積です。一方、給与の引き上げは将来にわたる継続的なコストとなります。会社の資金繰りが安定しているからといって、過去の利益の積み重ねである内部留保を安易に給与に回すと、将来の経営を圧迫するリスクが生じます。
- 内部留保は「いざという時の備え」内部留保は、経済の急変や不測の事態(パンデミック、自然災害など)に備えるための「経営のセーフティネット」としての役割が非常に大きいのです。特に日本では、「失われた30年」を経て、不確実性に備えるために内部留保を厚くする企業が増えました。社員の雇用を守るためにも、この備えは欠かせません。
- 内部留保を給料に回すと経営が停滞するリスクもし、内部留保を全て給与や配当に回した場合、企業は成長のための投資ができなくなります。新しい技術開発や設備投資、優秀な人材の獲得ができなければ、企業の競争力は低下し、結果として事業の縮小や倒産につながる可能性もあります。
経営者が知るべき、内部留保を対外的に説明するヒント
従業員や取引先あるいは社会に対して「なぜ内部留保を積み上げるのか」「速やかに還元しないのか」を明確に説明できるように備えること。これは、経営者にとって、企業の信頼性を高めるために必須のポイントです。ここでは、よくある誤解を解消し、企業の真意を伝えるための3つのポイントをご紹介します。
1. 内部留保は「未来への先行投資」であることを伝える
「内部留保=貯金」という誤解を解くには、そのお金がどこに向かっているのかを具体的に示すことが効果的です。
- 「給与は未来の原資から。内部留保は未来への投資。」
- 給与のベースアップは、一度上げると簡単には下げられない未来への継続的なコストです。一方、内部留保は、未来の成長のために行う先行投資です。この二つを対比させて説明することで、給与と内部留保が異なる性質を持つことを明確に伝えられます。
- 投資の中身を具体的に語る
- 「この内部留保は、新しい技術を開発するための研究費用や、より働きやすい環境を整えるための設備投資に回しています。これは、将来的に企業を成長させ、結果として社員の雇用や給与をさらに安定させるためのものです。」のように、投資の中身を具体的に示すことで、従業員も納得しやすくなります。
2. 「経営のセーフティネット」としての役割を強調する
不測の事態に備えることの重要性を、従業員の雇用を守る視点から説明します。
- 「社員とその家族の未来を守るための備え」
- 「内部留保は、経営が悪化した際に社員の給与や雇用を守るための、いわば経営の命綱です。過去に多くの企業が、急な経済危機で社員の雇用を守れなかった歴史があります。私たちは、その反省から、いざという時に備えることを重視しています。」と、過去の教訓を交えて説明することで、説得力が増します。
3. 内部留保とキャッシュフローを分けて説明する
内部留保が必ずしも潤沢な現金ではないことを、会社の資金繰りと紐づけて説明します。
- 「帳簿上の数字と、手元の現金の区別」
- 「貸借対照表の利益剰余金(内部留保)は、会社の過去からの利益の積み重ねで、すでに設備や事業投資として形を変えています。例えば、新しく買った機械も、帳簿上は内部留保の一部です。これを今すぐ現金化して給料に回すことはできません。」と、会計上の概念と現実の資金繰りの違いを明確に伝えることが重要です。
まとめ
「内部留保」とは、単に企業が現金を貯め込んでいるわけではありません。それは、企業の持続的な成長と安定のために不可欠な「経営資源」です。
過去の利益の積み重ねである内部留保は、将来の継続的なコストとなる給与とは性質が異なり、経済の急変時に社員の雇用を守る「セーフティネット」であり、未来の競争力を高めるための「先行投資」でもあります。
この役割を正しく理解し、対外的に明確に説明できるようになることが、経営者として従業員や社会との信頼関係を築く上で、重要なポイントとなるでしょう。
参考出典